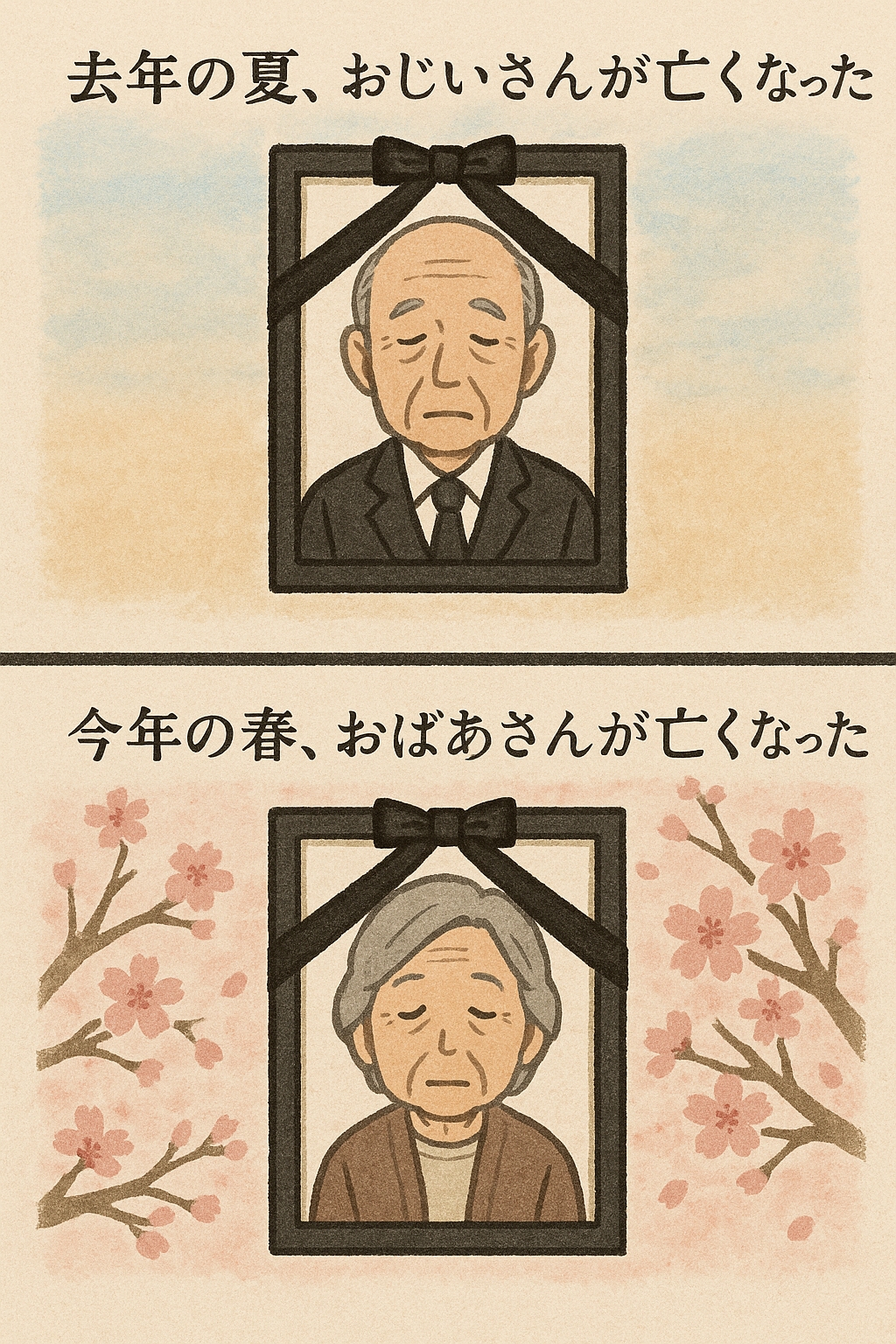短期間に二次相続が発生した場合の配偶者控除と相次相続控除の選択
両親が高齢の場合、短期間に連続して父母の相続が発生することは珍しくありません。このような場合、相続税の負担を最小限に抑えるためには、適切な税額控除の選択が重要です。本記事では、一次相続(父の相続)が未分割のまま二次相続(母の相続)が発生した場合を例に、配偶者の税額軽減と相次相続控除の適用について解説し、トータルの相続税を軽減するための選択肢を検証します。
一次相続が未分割の場合の遺産分割協議
一次相続(例えば父の相続)が発生し、遺産が未分割のまま短期間に二次相続(母の相続)が発生した場合、父の遺産分割協議には母の相続人が代わって参加します。具体的には、子がいる場合、子(相続人)全員の合意により、母が相続する財産の額を決定できます。このような状況では、配偶者の税額軽減を適用するか、相次相続控除を適用するかによって、トータルの相続税額が大きく異なることがあります。
配偶者の税額軽減と相次相続控除とは
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続する財産について、一定の条件を満たす場合に相続税を軽減する制度です。一方、相次相続控除は、被相続人が死亡前10年以内に相続により財産を取得し、相続税が課されていた場合に、二次相続の税額から一定額を控除する制度です。この二つの制度の選択によって、相続税の総額が大きく変わることがあります。
設例:相続税の計算例
以下に、具体的な設例をもとに、配偶者の税額軽減と相次相続控除の適用による相続税の違いを比較します。
- 被相続人:父(令和7年3月死亡)、母(令和7年5月死亡)
- 父の遺産:10億円
- 母固有の財産:4億円
- 相続人:母、長男、長女
【表1】配偶者の税額軽減制度を適用する場合
配偶者の税額軽減を適用する場合、配偶者が1円も相続しない選択をすることで、一次相続の税額が0円となり、トータルの相続税が最も少なくなります。ただし、この場合、相次相続控除は適用できません。以下は、配偶者の税額軽減を適用した場合の税額例です。
| 相続割合(母:子) | 一次相続の税額(万円) | 二次相続の税額(万円) ③ |
合計税額(万円) ①+②+③ |
|
|---|---|---|---|---|
| 母① | 子② | |||
| 10:0 | 17,810 | 0 | 32,786 | 50,596 |
| 9:1 | 14,248 | 3,562 | 33,128 | 50,938 |
| 8:2 | 10,686 | 7,124 | 33,472 | 51,282 |
| 7:3 | 7,124 | 10,686 | 33,814 | 51,624 |
| 6:4 | 3,562 | 14,248 | 34,158 | 51,968 |
| 5:5 | 0 | 17,810 | 34,500 | 52,310 |
| 4:6 | 0 | 21,372 | 29,500 | 50,872 |
| 3:7 | 0 | 24,934 | 24,500 | 49,434 |
| 2:8 | 0 | 28,496 | 19,710 | 48,206 |
| 1:9 | 0 | 32,058 | 15,210 | 47,268 |
| 0:10 | 0 | 35,620 | 10,920 | 46,540 |
※税額は1万円未満を四捨五入しています。
【表2】配偶者の税額軽減を適用せず、相次相続控除を適用する場合
配偶者の税額軽減を適用せず、相次相続控除を適用する場合、配偶者が全ての財産を相続することでトータルの相続税が最も少なくなります。一次相続で配偶者が納付した相続税は、二次相続で債務として控除され、かつ相次相続控除として税額控除されます。以下は、その場合の税額例です。
| 相続割合(母:子) | 一次相続の税額(母/子)(万円) | 二次相続の税額(万円) | 合計税額(万円) |
|---|---|---|---|
| 10:0 | 35,620 / 0 | 6,070 | 41,690 |
| 9:1 | 32,058 / 3,562 | 6,414 | 42,034 |
| 8:2 | 28,496 / 7,124 | 6,756 | 42,376 |
| 7:3 | 24,934 / 10,686 | 7,100 | 42,720 |
| 6:4 | 21,372 / 14,248 | 7,442 | 43,062 |
| 5:5 | 17,810 / 17,810 | 7,786 | 43,406 |
| 4:6 | 14,248 / 21,372 | 8,130 | 43,750 |
| 3:7 | 10,686 / 24,934 | 8,716 | 44,336 |
| 2:8 | 7,124 / 28,496 | 9,380 | 45,000 |
| 1:9 | 3,562 / 32,058 | 10,046 | 45,666 |
| 0:10 | 0 / 35,620 | 10,920 | 46,540 |
※相続税額の計算には相次相続控除を適用し、税額は1万円未満を四捨五入しています。
計算式の詳細
一次相続の税額
10億円(父の遺産) – 4,800万円(基礎控除額) = 95,200万円(課税遺産総額)
配偶者が全額相続した場合:35,620万円(配偶者が納付する相続税額)
二次相続の税額
(10億円(父の遺産) + 4億円(母固有の財産) – 35,620万円(一次相続の税額)) – 4,200万円(基礎控除額) = 100,180万円(課税遺産総額)
(100,180万円 × 1/2 × 50% – 4,200万円(控除額)) × 2人 = 41,690万円(合計税額)
41,690万円 – 35,620万円(相次相続控除額) = 6,070万円(二次相続の税額)
有利不利の判定のポイント
短期間に父母の相続が連続して発生した場合、以下の点を考慮して相続税の有利不利を慎重に判定する必要があります。
- 母固有の財産の状況:母が保有する財産の額や種類によって、税額控除の効果が変わります。
- 配偶者の相続割合:一次相続で配偶者がどの程度の財産を相続するかによって、税額が変動します。
- 税額控除の選択:配偶者の税額軽減を適用するか、相次相続控除を適用するかで、トータルの税額が大きく異なります。
特に、配偶者が全額相続し相次相続控除を適用するケース(表2の10:0の場合)では、合計税額が41,690万円となり、配偶者の税額軽減を適用した場合(表1の0:10の場合)の46,540万円に比べて約4,850万円も税額が軽減されることがわかります。
まとめ
短期間に連続して相続が発生する場合、配偶者の税額軽減と相次相続控除のどちらを選択するかは、慎重なシミュレーションが必要です。相続人の状況や財産の構成に応じて、最適な選択を行うことで、トータルの相続税負担を軽減できます。相続税の計算や控除の適用は複雑なため、専門家である税理士に相談することを強くおすすめします。当事務所では、相続税の最適化に向けた具体的なアドバイスを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。