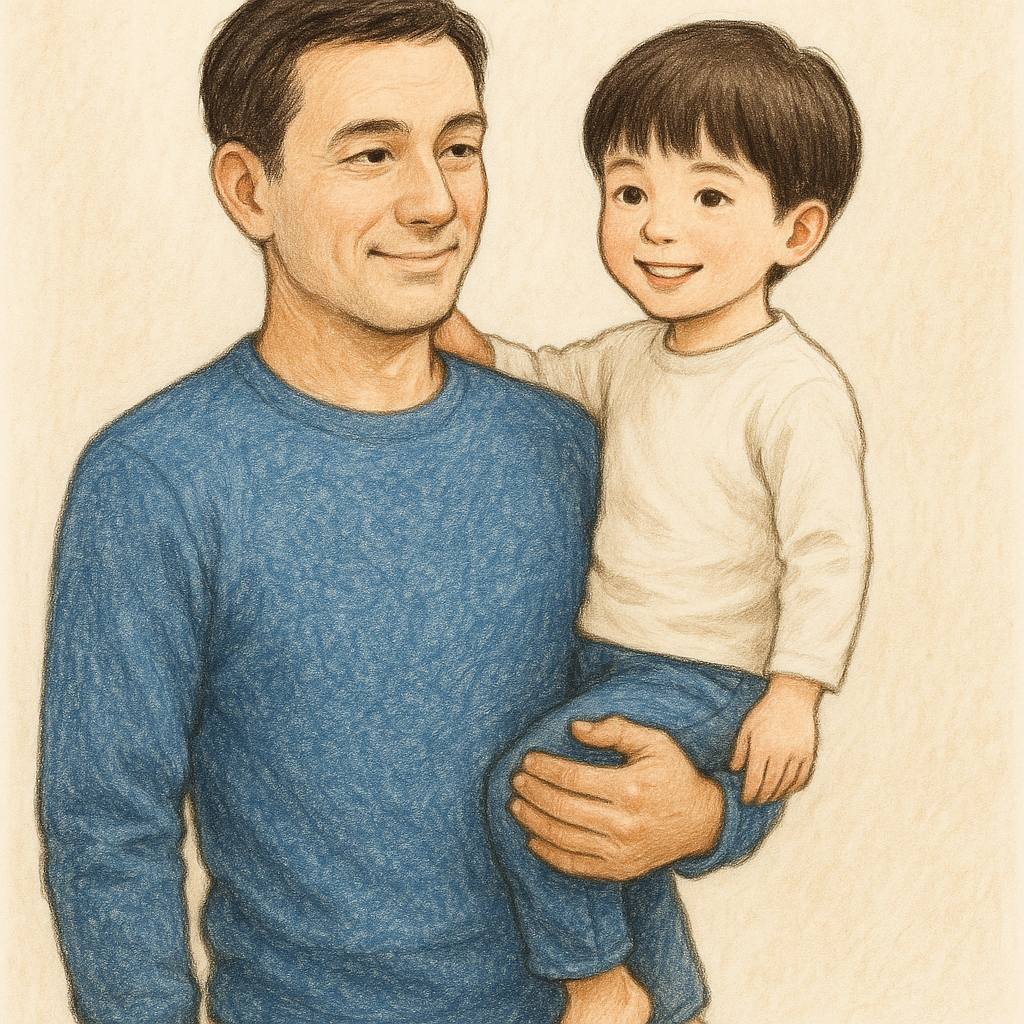健康保険の令和7年度被扶養者資格再確認の重要性と手続きガイド
毎年実施される「被扶養者資格再確認」は、健康保険制度の適正な運営と保険料負担の軽減を目的とした重要な手続きです。この記事では、令和7年度の被扶養者資格再確認の目的、対象者、確認方法、提出期限について詳しく解説します。事業主や健康保険の被保険者の皆様にとって、保険料負担の適正化や制度の透明性向上に役立つ情報をお届けします。
被扶養者資格再確認とは?
被扶養者資格再確認は、協会けんぽが健康保険法施行規則第50条に基づき、被保険者の扶養家族(被扶養者)が引き続き扶養の条件を満たしているかを確認する手続きです。この確認作業は、加入者情報の正確性を保ち、保険給付の適正化を図るために毎年行われます。被扶養者の状況が就職や収入の増加などで変化する場合があるため、定期的な確認が不可欠です。
この手続きは、単なる現況確認にとどまらず、事業主や被保険者の保険料負担軽減や高齢者医療制度の拠出金の適正化につながる重要な役割を果たします。
被扶養者資格再確認の2つの目的
被扶養者資格再確認には、以下の2つの大きな目的があります。
目的1:加入者記録の適正化
被扶養者の認定要件には、被保険者の収入によって生計を維持されていることや、一定の収入基準を満たすことなどが含まれます。しかし、就職や収入増加により、これらの条件を満たさなくなる場合があります。このようなケースを適切に見極め、扶養から外すことで、加入者記録を正確に保ちます。これにより、健康保険制度の透明性が向上し、保険料の適正な運用が可能となります。
目的2:高齢者医療制度における拠出金の適正化
協会けんぽは、65歳以上の高齢者の医療費を支えるために「拠出金」を負担しています。この拠出金の金額は加入者数に基づいて算定されるため、被扶養者の数が正確であることが重要です。拠出金には以下の2種類があります。
- 後期高齢者支援金:75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するための資金。被用者保険間では総報酬按分により負担が決定されます。
- 前期高齢者納付金:65歳~74歳の高齢者が加入する保険者間で、加入者の偏在による負担の不均衡を是正するための資金。一部は総報酬按分により算定されます。
正確な加入者数を把握することで、拠出金の負担を適正化し、保険料負担の軽減につなげることができます。
令和7年度被扶養者資格再確認の概要
1. 実施時期
令和7年10月下旬から、協会けんぽより事業主様へ「被扶養者状況リスト」が順次送付されます。対象者がいない場合はリストの送付はありません。
2. 再確認の対象者
以下の条件に該当する被扶養者が再確認の対象となります。
- 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
- 同居が扶養認定の要件である続柄の方で、被保険者と別居している可能性が高い方
- 令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)を超過している方(18歳未満や直近で認定された方を除く)
3. 確認方法
事業主様は、送付された「被扶養者状況リスト」を基に、被保険者を通じて対象の被扶養者が健康保険の要件を満たしているか確認してください。確認結果をリストに記入し、同封の返信用封筒でご提出ください。
4. 確認観点
以下の3つの観点で確認を行ってください。
観点1:他の健康保険に加入していないか
以下の状況を確認し、必要に応じて手続きを行ってください。
| 状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 被扶養者が就職し、他の健康保険組合等の被保険者資格を有しているが、扶養解除手続きを行っていない | 扶養の解除手続き |
| 新たに被扶養者となったが、以前加入していた他の健康保険を脱退していない | 他の健康保険の脱退手続き |
| 同一の被扶養者が被扶養者状況リストに重複して記載されている | 扶養認定日を確認するため、協会けんぽ支部へ連絡 |
観点2:同居が必要な続柄の者が別居していないか
以下の続柄の方は、被保険者と同居していることが扶養認定の要件です。別居している場合は、扶養解除手続きが必要です。
- 同居が不要:配偶者、子、孫、父母、祖父母、曾祖父母、兄姉弟妹
- 同居が必要:上記以外の続柄(例:伯叔父母など)
観点3:被扶養者の年収が収入要件を満たしているか
以下の基準で年収を確認してください。
- 同居の場合:被扶養者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円、19歳以上23歳未満は150万円)未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること。
- 別居の場合:被扶養者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円、19歳以上23歳未満は150万円)未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと。
- 年収超過の場合:年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円、19歳以上23歳未満は150万円)を超過している場合、人手不足による労働時間延長など一時的な収入増加であれば、事業主の証明書を提出することで扶養継続が可能です。ただし、3年連続で超過する場合は扶養解除が必要です。
厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づき、一時的な収入変動の場合は事業主の証明書(詳細はこちら)を提出してください。
5. 扶養解除の手続き
扶養解除が必要な場合は、日本年金機構へ電子申請で「被扶養者異動届」を提出してください。電子申請が難しい場合は、被扶養者状況リストに同封の「被扶養者調書兼異動届」に記入し、保険証等(お持ちの場合)を添えて提出してください。紙媒体の提出の場合、決定通知書の返送に1~2か月かかる場合がありますので、お急ぎの場合は日本年金機構事務センターへ直接提出してください。
6. 提出期限
令和7年12月12日(金曜日)までに、被扶養者状況リストをご提出ください。対象者がいない場合も、リストの提出が必要です。
なぜ被扶養者資格再確認が重要なのか?
被扶養者資格再確認は、保険料負担の軽減と健康保険制度の持続可能性に直結します。扶養条件を満たさない方が登録されたままだと、拠出金の額が過大に算出され、事業主や被保険者の保険料負担が増加します。適正な確認により、こうした負担を軽減し、公平な制度運営が可能となります。また、高齢者医療制度の拠出金は加入者数に基づくため、正確なデータが制度全体の効率性を支えます。
事業主・被保険者の皆様へのお願い
被扶養者資格再確認は、皆様のご協力があってこそ成り立つ手続きです。協会けんぽから送付される書類に正確な情報を記入し、期限内に提出をお願いいたします。詳細は協会けんぽの公式ホームページや日本年金機構のホームページをご確認ください。
まとめ
令和7年度の被扶養者資格再確認は、加入者記録の正確性確保と保険料負担の軽減を目的とした重要な手続きです。事業主や被保険者の皆様のご協力により、健康保険制度の健全な運営が支えられます。