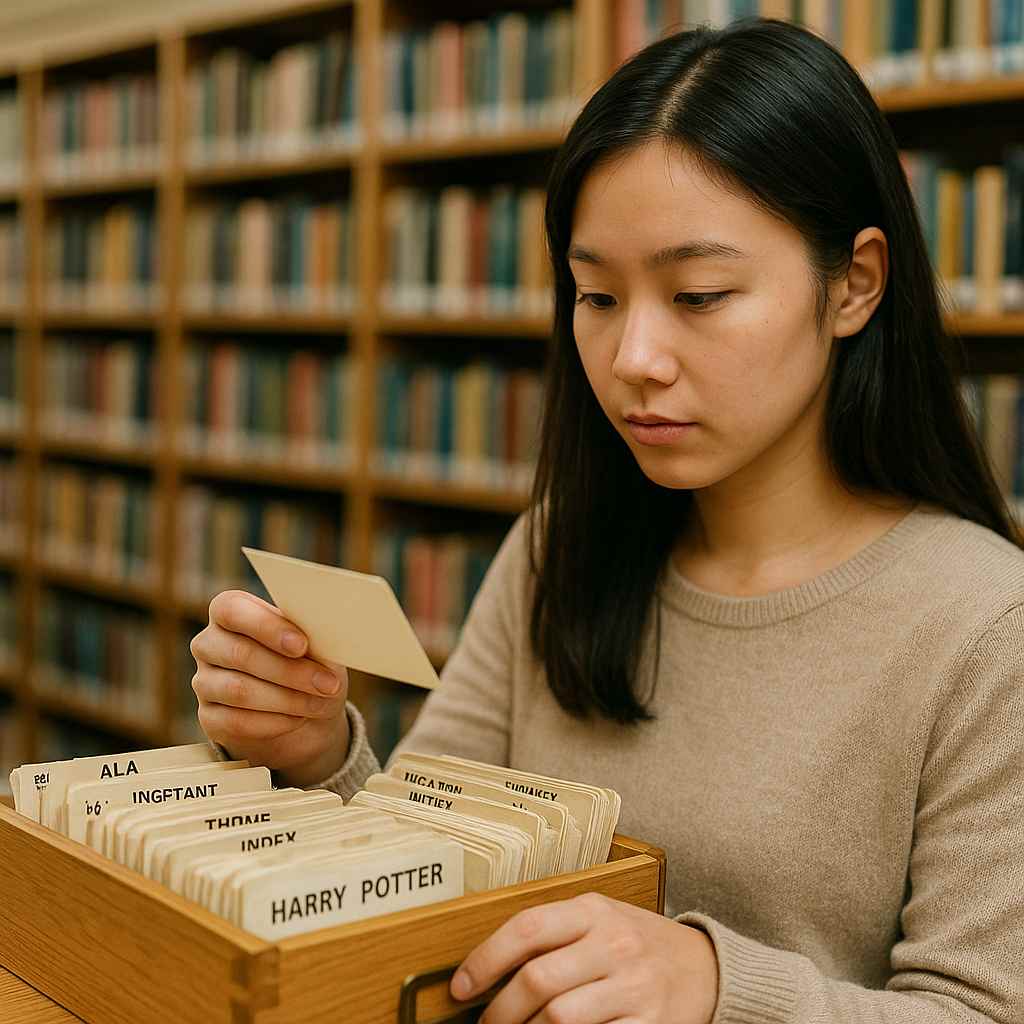借入金の効果的な管理:経営指標とよくある疑問を解説
前回の記事「自社の借入金をチェック!確認ポイントと管理のコツ」では、借入金の区分や管理のポイントを紹介しました。今回は、借入金の管理をさらに深めるために、金融機関が注目する経営指標と、借入金の返済に関するよくある疑問について解説します。適切な借入金管理は、資金繰りの安定だけでなく、金融機関からの信頼獲得や経営改善の基盤となります。さっそく、具体的なポイントを見ていきましょう。
1. 金融機関が注目する経営指標を理解する
借入金の管理において、自社の財務健全性を示す経営指標は、資金繰りの見える化や金融機関との信頼関係構築に欠かせません。以下の2つの指標を押さえておきましょう。
(1)債務償還年数
債務償還年数は、借入金を返済するのに何年かかるかを示す指標で、企業の返済能力を測る重要な目安です。金融機関はこの指標を融資判断の基準として重視します。簡易的な計算式は前回の記事で紹介した「借入金総額 ÷ (当期利益 + 減価償却費)」ですが、より詳細な計算式として「TKC経営指標(BAST)」では以下のように定義されています。
この数字が小さいほど、返済能力が高いことを示します。中小企業庁などでは「10年以内」を目安としており、これを超える場合は返済負担が重い可能性があります。例えば、債務償還年数が15年であれば、現在の利益水準では借入金の完済に時間がかかりすぎるため、経営改善や借り換えを検討する必要があります。
(2)EBITDA有利子負債倍率
企業の本業から得られる利益(償却前営業利益:EBITDA)と借入金のバランスを示すのが「EBITDA有利子負債倍率」です。この指標は、企業の財務の安全性を評価する際に用いられます。計算式は以下の通りです。
この数字が小さいほど、財務の安全性が高いことを示します。中小企業庁では「15倍以内」を目安としており、15倍を超えると、現在の利益水準で借入金を返済するのに長期間を要するため、資金繰りが厳しくなるリスクがあります。例えば、借入金が多額で営業利益が少ない場合、この倍率が高くなり、追加融資のハードルが上がる可能性があります。
2. よくある疑問:借入金の返済はなぜ費用にならないのか?
「借入金を返済しても利益が減らないのはなぜ?」「返済は費用ではないの?」といった質問を耳にすることがあります。この疑問を解消するために、借入金の会計処理の基本を解説します。
借入金は、会社が外部から一時的に借りたお金であり、将来的に返済する義務がある「負債」です。返済は、借りたお金を返す行為に過ぎず、会社の資産(現金)が減る一方で負債(借入金)も同額減少するため、損益には影響しません。会計上、「費用」とは収益を得るために発生する支出(例:仕入、人件費、家賃)であり、借入金の返済はこれに該当しません。一方、借入金の利息は、借入れに伴うコストとして「支払利息」などの勘定科目で費用計上されます。
借方:(借入金)500万円
(支払利息)5万円
貸方:(普通預金)505万円
この場合、支払利息5万円のみが費用として損益計算書に反映され、借入金500万円の返済は貸借対照表の負債と資産の減少として処理されます。
借入金の入金も「収益」にはなりません。借入時に受け取った資金は「負債」として計上され、会社の資産(現金・預金)が増えるだけです。この点も、借入金が損益に直接影響しない理由です。
借入金管理の次のステップ
経営指標を活用して借入金の返済能力を把握し、会計処理の基本を理解することで、資金繰りの安定と金融機関との信頼関係が強化されます。以下のアクションを検討しましょう。
- 定期的な指標チェック:債務償還年数やEBITDA有利子負債倍率を毎期計算し、10年や15倍以内に収まるよう経営計画を見直す。
- 財務情報の開示:決算書や試算表を金融機関に定期的に提出し、最新の経営状況を共有。TKCモニタリング情報サービスを活用すると効率的です。
- 専門家の相談:借入金の管理や経営指標の改善が難しい場合、税理士や会計士に相談して具体的な改善策を策定する。
借入金の適切な管理は、持続可能な経営の基盤です。当事務所では、経営指標の算出や財務改善のサポートを行っています。資金繰りや借入金管理でお悩みの場合は、ぜひご相談ください。