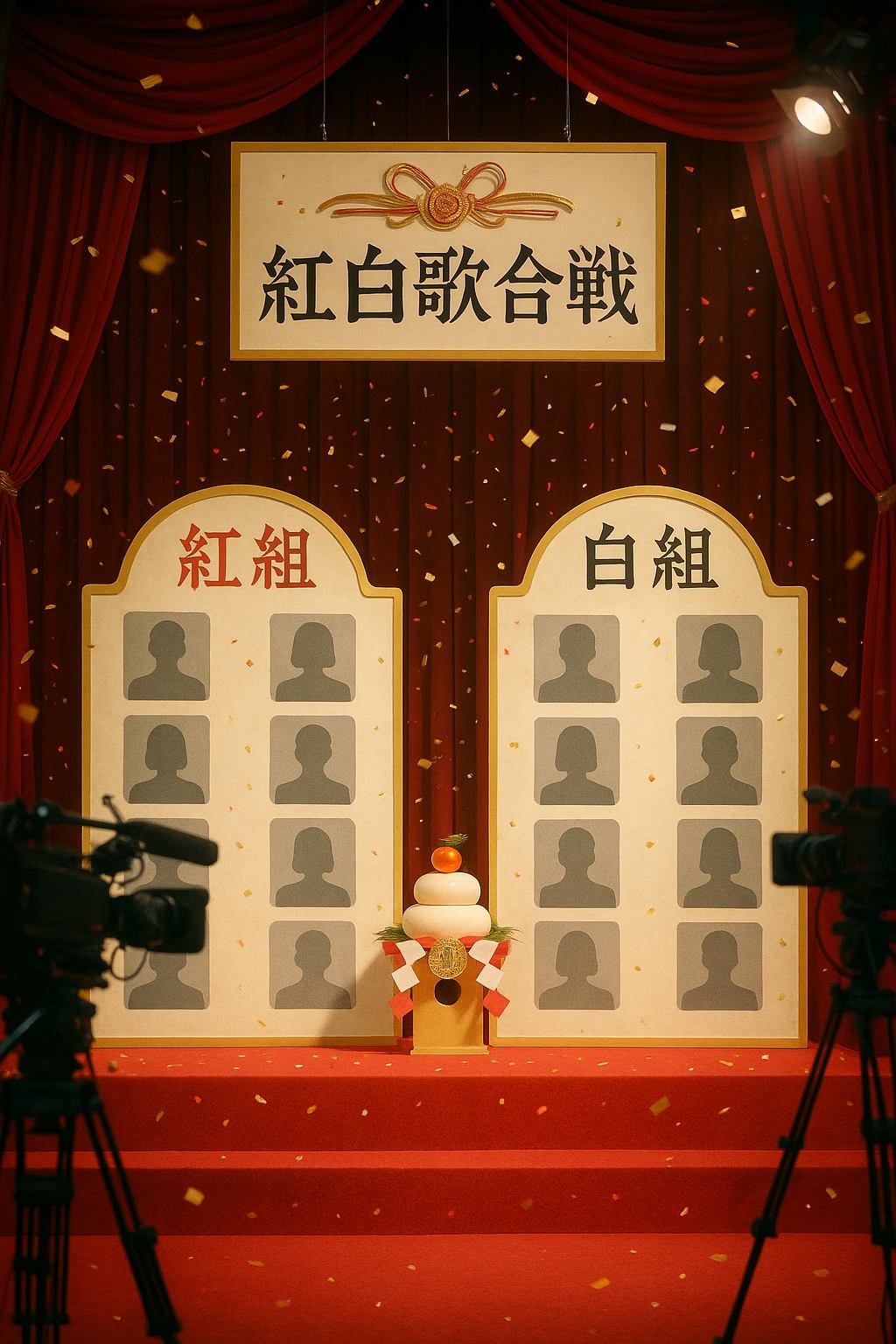最終確認! 税理士事務所の年末調整アドバイス
当税理士事務所では、企業様の円滑な税務処理をサポートしています。令和7年分(2025年)の年末調整は、昨年のルールと同じと思い込まず、最新の変更点をしっかり確認しましょう。本記事では、巡回監査時や従業員指導のポイントを詳しく解説します。年末調整後の修正を避けるため、申告書の記載事項と控除額を従業員に徹底的に確認してください。また、事務負担軽減のための電子化もおすすめです。
1. 基礎控除申告書の注意点
基礎控除申告書の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算」欄は、所得の正確な把握が鍵です。誤った記載で控除額が変わる可能性があるため、慎重に。
- 給与以外の所得(一時所得、雑所得など)の扱い: これらがある場合、「給与所得以外の所得の合計額」欄に記載。ただし、源泉分離課税の対象となる所得や、確定申告を選択しない一定の所得は除外されます。例えば、株の配当金(源泉分離課税)や少額の雑所得は含めないよう注意。
- 副業などの複数給与: 2か所以上から給与を受けている場合、全てを合算して「給与所得」欄に記入。副業収入を申告し忘れると、過少申告となり、後で税務署から指摘されるリスクがあります。従業員には、副業の有無を事前に確認するようアドバイスしましょう。
2. 所得金額調整控除申告書の注意点
所得金額調整控除は、給与収入850万円超の納税者を対象とした負担軽減措置です。令和7年も引き続き適用され、子どもや障害者を持つ家庭に有利。国税庁のNo.1411によると、2種類の控除があり、年末調整で適用できるのは「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」のみです。
- 対象者: 年中給与収入が850万円を超え、(a) 本人が特別障害者、(b) 23歳未満の扶養親族あり、(c) 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族ありのいずれか。
- 控除額の計算: {給与収入(上限1,000万円) – 850万円} × 10%。例えば、給与収入900万円の場合、(900万 – 850万) × 10% = 5万円の控除。
- 複数該当の場合: 申告書にチェックするのは1つだけ。扶養親族が複数いる場合も、1人を記載。
- 夫婦両方の適用可能: 扶養控除とは異なり、夫婦ともに850万円超で23歳未満の子がいる場合、両方が控除を受けられます。これにより、共働き世帯の税負担が軽減されます。
詳細は国税庁タックスアンサーNo.1411「所得金額調整控除」 およびNo.2676「年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき」をご確認ください。
3. 保険料控除申告書の注意点
保険料控除は、生活保障のための支出を税制優遇するもの。契約内容の確認を怠ると、控除が無効になる場合があります。
- 一般生命保険・介護医療保険: 保険金の受取人が納税者本人、配偶者、または親族であること。友人名義の契約は対象外。
- 個人年金保険: 年金の受取人が納税者本人または配偶者限定(親族除く)。老後資金形成を促すための厳格なルールです。
- 地震保険料控除: 「保険対象の家屋等に居住・家財利用者の氏名」欄に、納税者本人または生計一親族の氏名を記載。共有名義の家屋の場合、全員分を記入。
4. マイカー通勤の非課税限度額引き上げについて
注意!令和7年4月1日以降適用で、年末調整対応が必要です。
令和7年8月7日の人事院勧告を受け、国税庁は通勤手当の非課税限度額を改正。令和7年4月に遡及適用され、年末調整で調整します。従業員の通勤距離を確認し、超過分を課税対象に調整。最新情報は国税庁サイトで確認を。
まとめとアドバイス
年末調整はミスが後々のトラブルを招くため、「去年と同じ」ではなく、最新ルールを適用。申告書以外の記載も従業員に確認を促し、電子化(e-Taxや専用ソフト活用)で効率化を図りましょう。当事務所では、年末調整の相談・代行を承っています。お気軽にご連絡ください。
参考:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」