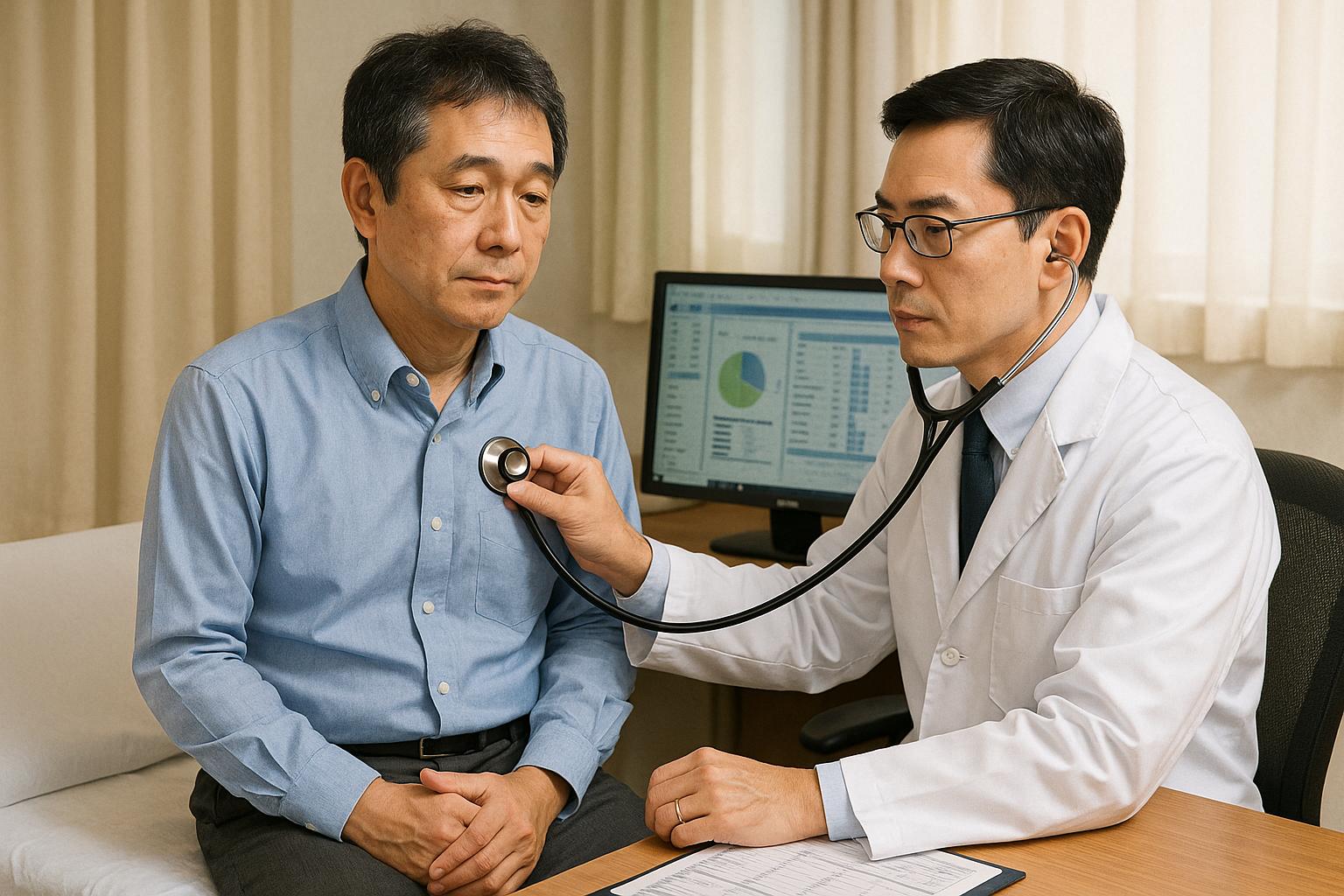福利厚生費とは?税務上のポイントを徹底解説(2)
企業が従業員や役員に対して提供する福利厚生は、働きやすい環境を整えるための重要な施策です。しかし、税務上では「福利厚生費」として認められるためには、特定の要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合、給与や役員報酬として課税対象となるため、慎重な対応が求められます。この記事では、特に社宅の貸与や人間ドックの費用負担に焦点を当て、税務上のポイントを詳しく解説します。
1. 従業員への社宅・寮の貸与
従業員に社宅や寮を提供する場合、適切な家賃を受け取ることで給与課税を回避できます。以下に、具体的な要件と計算方法を説明します。
(1) 賃貸料相当額とは
賃貸料相当額は、社宅の家賃が給与として課税されないための基準となる金額です。以下の3つの要素の合計で計算されます:
- 建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
- 12円 × (建物の総床面積(m²) ÷ 3.3m²)
- 敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
この金額を計算するためには、事前に貸主から固定資産税の課税標準額を確認しておくことが重要です。
(2) 給与として課税されるケース
社宅の提供方法によって、課税対象となる場合があります。以下に主なケースを挙げます:
ケース1:無償で社宅を提供
賃貸料相当額全額が給与として課税されます。ただし、看護師や守衛など、業務上社宅に住む必要がある従業員に対して無償で提供する場合、課税されないケースもあります。
ケース2:賃貸料相当額より低い家賃を受け取る
従業員から受け取る家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、差額は課税されません。しかし、50%未満の場合は差額が給与として課税されます。
ケース3:住宅手当や従業員が直接契約する家賃負担
これらは社宅の貸与とは認められず、支給額全額が給与として課税されます。
2. 役員への社宅の貸与
役員に対して社宅を提供する場合も、従業員と同様に賃貸料相当額を受け取ることで給与課税を回避できます。ただし、社宅の規模や豪華さによって計算方法が異なります。
(1) 小規模な住宅の賃貸料相当額
小規模な住宅(法定耐用年数30年以下で床面積132m²以下、または30年超で99m²以下の住宅)の場合、従業員と同じ計算式で賃貸料相当額を算出します。区分所有の建物では、共用部分の床面積を按分して計算します。
(2) 小規模でない住宅の賃貸料相当額
小規模でない住宅の場合、以下のように計算方法が異なります:
- 自社所有の社宅
賃貸料相当額 = (建物の固定資産税の課税標準額 × 12% [30年超の場合は10%]) + (敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%) ÷ 12 - 他から借り受けた住宅
賃貸料相当額 = 家主に支払う家賃の50%と上記自社所有の計算額のいずれか高い方
(3) 豪華社宅の判定
床面積が240m²を超える住宅や、プールや役員の嗜好を強く反映した設備がある場合は「豪華社宅」とみなされます。この場合、通常の賃貸料相当額ではなく、通常支払うべき使用料に相当する額が課税対象となります。豪華社宅の判定には、取得価額や内外装の状況なども考慮されます。
3. 人間ドックの費用負担
成人病予防のための人間ドックの費用を会社が負担する場合、給与課税の対象となるかどうかは、以下の国税庁の質疑応答事例に基づいて判断されます。
質疑応答事例:人間ドックの費用負担
A社では、社内規程に基づき、全役員・従業員を対象に春秋2回の健康診断を実施し、35歳以上の希望者全員に2日間の人間ドックを提供。専門医療機関で実施し、費用は会社が負担。この場合、検診料は給与として課税されるか?
回答
給与として課税する必要はありません。特定の役員や地位にある人のみを対象とする場合は課税対象となりますが、一定年齢以上の希望者全員が受診でき、費用を一律に負担する場合は課税されません。
このように、社内規程を整備し、全従業員を対象とした健康管理の一環として人間ドックを実施することで、税務上のリスクを回避できます。
まとめ:税務リスクを回避するためのポイント
福利厚生費として認められるためには、税務上の要件を正確に理解し、適切な運用を行うことが重要です。特に以下の点に注意しましょう:
- 社宅の貸与では、賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取る。
- 豪華社宅に該当しないよう、設備や規模を確認する。
- 人間ドックの費用負担は、特定の役員や従業員に限定せず、希望者全員を対象とする。
- 社内規程を整備し、税務上の根拠を明確にしておく。
税務調査で指摘を受けないためにも、事前に専門家に相談し、適切な対応を行うことをお勧めします。澤田匡央税理士事務所では、福利厚生費の税務対応に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。