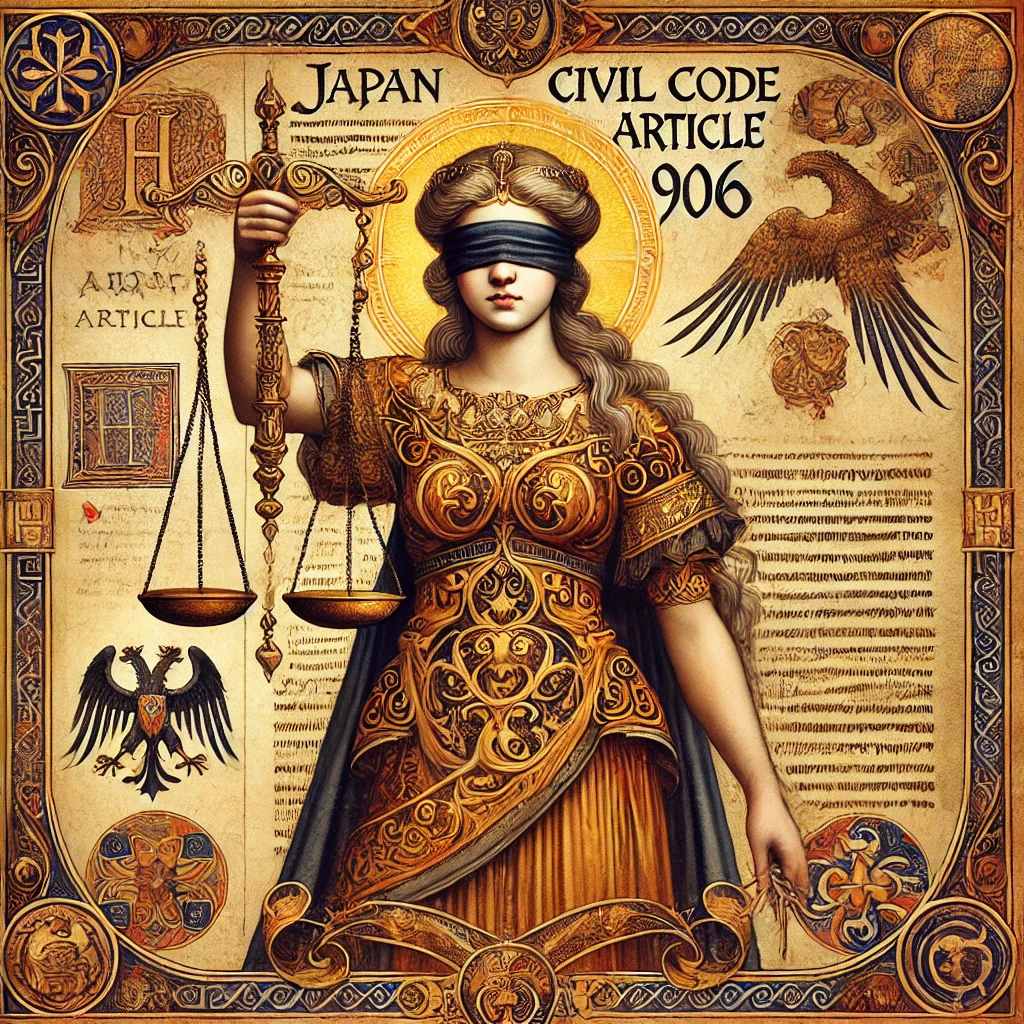遺産分割のスタートは民法第906条
「自分の財産を誰にどれだけ残すか」という意思表示を、法的効力のある書面として残したものが遺言書です。
相続人間のトラブルを防止し、スムーズな相続にも効果を発 揮しますが、税務への影響もあるため、遺言書作成に関する知識も備えておくと良いでしょう。
遺産分割のスタートは民法第906条
遺産の分割について、 民法第906条では次のように定められています。
(遺産の分割の基準)
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、 各相続人の年齢、職業、 心身 の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
これは、「どの財産を、どの相続人に分割すべきか」を決めるときに照らし合わせる基準を示したものです。 遺言書がない場合、「遺産分割=法定相続分で分ければよい」と思われがちですが、あくまでもこの民法第906条に定められた基準がスタートとなります。遺産分割協議の際は、この条文を念頭に置いて進める必要があるでしょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、決められた様式で遺言書を作成する必要があります。
(1) 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の様式
○用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない。
○上側5mm、下側10mm、 左側20mm、 右側5mmの余白を確保する。
○遺言書本文、 財産目録には、 各ページに通し番号でページ番号を記載する。
○複数ページでも綴じ合わせない。
(2) 自筆証書遺言書を作成するときの注意事項
○誰に、どの財産を残すか財産と人物を特定して記載する。
○財産目録を添付する場合は、 別紙1、 別紙2などとして財産を特定する。
○財産目録にコピーを添付する場合は、その内容が明確に読み取れるように鮮明に写っていることが必要。
○推定相続人の場合は「相続させる」 または 「遺贈する」、 推 定相続人以外の者に対しては「遺贈する」と記載する。
法務省Webサイト 「自筆証書遺言書保管制度03 遺言書の様式等についての注意事項」
遺言書の作成にあたっては税務への影響もありますので、税理士にお声掛けください。